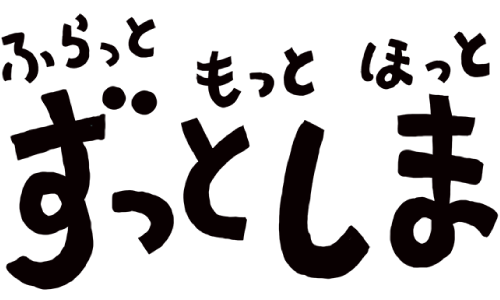


「椿の島」として知られる利島村には、村内唯一の保育園があります。ここでは、島の豊かな自然を活かした遊びや地域と連携した保育が行われています。
「子どもたちが大きくなっても、利島に住んでいたことを忘れないでほしい」
そんな想いを胸に、日々子どもたちと向き合っている川村里美さんにお話を伺いました。
川村さんが保育士を目指したきっかけは、幼い頃にまで遡ります。
母親が保育園の給食を作る調理師だったこともあり、保育園はとても身近な存在でした。
「一人っ子だったこともあって、ずっと兄弟が欲しかったんです。だから、年長くらいのころには、0歳児のクラスに行って先生のお手伝いをしていました。おうちに帰ってからも、ぬいぐるみを並べて『お昼寝の時間ですよ』と言って寝かしつけたりしてましたね。」
幼い頃からずっと憧れていた保育士という仕事。
大きくなってからもその想いは変わらず、資格を取得し、保育園で働き始めました。
しかし、現実は思い描いていたものとは少し違っていたようです。
「いざ働き始めると、思っていたものとは違う部分もあって…。20代の頃に一度挫折して、しばらく事務の仕事をしていました。10年以上、保育の現場からは離れていたんですが、ずっと保育士に戻りたいという気持ちが消えなくて、求人を検索してみたんです。」
そこで偶然目に留まったのが、利島村の保育士募集ページでした。
「検索したとき、一番最初に出てきたのが利島村の保育士募集だったんです。『これは何かの縁かな?』と思って応募してみました。ちょうどその時、第三セクターで働いていて、全国の市区町村に冊子を送るために色々調べていたので、利島の存在は知っていたんです。」
さらに、もうひとつ「島との縁」を感じる出来事があったと言います。
「女子高出身なんですが、卒業旅行が大島だったんですよ(笑)。当時の学年主任の先生が大の船好きで、前の学年はディズニーランドに行ったのに、私たちはまさかの大島。そのときは『なんで私たちだけ!?』と思いましたが、大人になってみると、こうして島とつながることになるなんて不思議な縁ですよね。」

「40歳を過ぎると、保育士の求人はぐっと少なくなります。でも、利島村は年齢制限がないと聞いて、とりあえず履歴書を送ってみようと思いました。」
思いがけずつながった利島という場所。
この島で、もう一度「保育士」として歩み始めることになりました。
実際に利島での生活を始めて、どんな印象を持ったのでしょうか。
「思っていたよりも、すぐに馴染むことができました。皆さん、外から来た人をとても温かく迎え入れてくれるので、すごく住み心地が良いですね。それに、ご近所同士の物々交換がすごく懐かしくなったというか…まるで昔の暮らしに戻ったような感覚です。
ひとつ言うとすれば、暮らし始めた当時は、外食ができなかったことですかね。私が来たときは、まだお店も少なくて、どこで食べられるのか分からなかったんです。でも、島に来る前も1人暮らしをしていたので、そこまで問題でもなかったですね。」

川村さんが利島で暮らし始めて、約15年。
長い時間をかけて、島の子どもたちの成長を見守ってきたからこそ、感じることがあるようです。
「今、利島保育園には、1歳から小学校入学前の園児が8人います。以前は定員25名近くの子どもたちが在籍していたこともありましたが、今はだいぶ減ってしまいました。なかなか地元の人が戻ってこないので、純粋に島の家庭で育っている子は数人しかいないんです。
駐在さんや診療所、学校の先生のお子さんなど、数年ごとに引っ越してしまう子も多いんです。せっかく一緒に過ごしたのに、すぐにお別れになってしまうのはやっぱり寂しいですね。
だからこそ、子どもたちが大きくなったときに、利島で過ごした時間を思い出せるように、他ではできない体験や、在園児アルバムを作って、できるだけ多くの思い出を残してあげたいなと思っています。」

川村さんの「利島の思い出を子どもたちに残したい」という想いは、日々の保育活動にも表れています。
「ここ数年、特に力を入れているのが、利島の食材を使ったおやつ作りです。この前は、郷土料理『煮干し餅』を園児たちと一緒に作りました。蒸してミンチした後に干したサツマイモと、茹でて細かく切ったヨモギをつきたてのお餅に入れてよく混ぜたものなんですが、子どもたちにも大人気なんです。
昔ながらの作り方だと手間がかかってしまうので、子どもでも簡単に作れる片栗粉を使った「煮干し餅風焼き団子」を地域の人から教えてもらい、子どもたちと楽しく作りました。」
他にも、椿油の搾油体験や、椿の花びら染めなど、島にある素材を生かした遊びを積極的に行っています。
「保育士の人手が少なくなってきていることもあって、地域の方との交流もすごく大事だと感じています。特に農協さんには椿のことなど、いろいろ相談に乗ってもらっていますね。子どもたちも、普段から買い物に行く場所なので、顔馴染みの人が多いんです。」
園児たちが地域の人たちと自然につながりながら成長していく環境は、小さな島だからこそできる保育の形なのかもしれません。
様々な工夫を凝らして、園児の遊びをサポートする川村さん。子どもたちが島を巣立っていくとき、身につけてほしいことについて伺いました。
「やっぱり、自然を生かした体づくりをしていきたいなと思っています。椿山によく遊びに行くんですが、椿山の傾斜がすごくて、子どもたちは『天然の滑り台!』と言いながら楽しんでいます。また、下が落ち葉なので、保育士が確認して安全そうであれば、木登りにもチャレンジしています。
子どもって面白くて、『絶対に登れないよね』って思う椿山の斜面を、わざわざ選んで登るんですよ(笑)。どうしても、自分の可能性を試してみたくなるのでしょうね。ちょっと手を貸したり、子どもが諦めるまで挑戦させてみたりしながら、『できた!』という達成感を味わえるようにしています。」
挑戦する楽しさ、諦めない気持ち、そして成功したときの喜び。
島の大自然の中で、それらを学べる環境があるのは、とても贅沢なことなのかもしれません。

「私は、この利島の自然を目一杯使って、子どもたちと一緒に遊びを考えていきたいです。」
そう話す川村さんの目は、子どもたちと同じようにキラキラと輝いていました。
大きな遊具がなくても、自然が子どもたちの遊び場になり、地域の人々がみんなで見守る。
利島らしい遊びの一つひとつが、きっと子どもたちの心に色濃く刻まれていくのだと感じました。