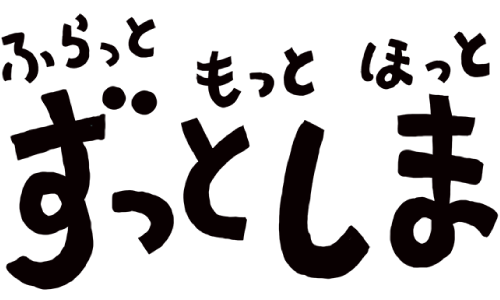


人口300人の利島には、小学校・中学校はわずか1校しかありません。
もともとは「小中併設校」でしたが、令和6年度から伊豆・小笠原諸島で初となる「※義務教育学校・利島小中学校」として再スタートしました。
※「義務教育学校」とは、小学校と中学校の義務教育9年間を一貫して行う学校のこと。前期課程(小学校に相当)と後期課程(中学校に相当)からなる。
利島村の学校教育に携わる方々は、地域特有の課題に向き合いながら、日々工夫を凝らして教育方針を模索・実践しています。その取り組みのひとつに、同じ東京都内の島々をつなぎ授業をする「オンライン授業」があります。
島の児童・生徒が、自分とは異なる考えや価値観に触れる機会をどうつくるか、小規模校ならではのさまざまな課題に向き合うなかで生まれたのが【島と島をつなぐオンライン授業】です。今回は実際に「オンライン授業」の授業風景を取材し、お二人の教員にもお話を伺いました。
令和7年度現在、利島小中学校の1学年あたりの児童・生徒数は平均2〜3人。きわめて少人数の「小規模コミュニティ」で学びを深めています。少人数校のメリットとしては、一人ひとりの個性や状況に合わせた指導がしやすく、親密な関係を築くことができるという点があげられます。一方で、人間関係が固定されやすく、新たな交流や多様な意見・考え方に触れる機会が少ないという課題も抱えています。
今回取材でお邪魔したのはオンライン授業を実践している3年生の教室。こちらには児童2人が在籍しています。(取材当時)
少人数校では、多様な意見を交わす場が限られてしまうことが懸念されます。例えば、国語の授業で扱われている「もっと知りたい友達のこと」という学習課題。こちらの目的は、自分のことを伝えたり、それに対して相手に質問をしたりすることです。しかし、利島の児童の場合は、その「自分」や「相手」のことをお互いにすでによく知っている場合が多く、児童が新しい発見や学びに繋がりにくいのです。そうなると、新たな意見との触れ合いが減少し、学びの幅がどうしても限られてしまいます。
そうした環境の中で他の地域の児童と交流し、同じ時間軸を共有することで、自分とは異なる視点や価値観、考え方に触れることができます。こうした体験は、学びの幅を広げると同時に、児童の興味・関心の幅も広げるきっかけになっていくのです。

義務教育学校となった利島小中学校
これまでも教室内でモニターを使ったオンライン授業は行われていましたが、担当教員同士のつながりをきっかけに個別での実施がほとんどだったそうです。そうした中、今年度からの新しい取り組みとして、東京都のオンラインマッチングサービスを活用することになりました。
6月中旬、教員間の掲示板やオンラインサポートシステムを通じて実現した道徳の授業、「おしゃべりすごろく」の様子を見学させていただきました。画面の向こうには同じ伊豆諸島の「式根島」と「御蔵島」にいる3年生の児童がいます。
授業の内容は、サイコロを振って、当たったマスの質問に答えていくすごろく形式。画面共有機能を活用して、モニターには児童たちのお互いの顔とすごろく画面が映し出され、質問への回答や、それに対する意見交換が行われていました。画面越しに聞こえる笑い声や問いかけに対して、緊張しながらも笑顔で、会話のキャッチボールを楽しんでいる様子が見受けられました。

別の日には、社会科の「もっと知りたい島のこと」という授業で島の良いところを発表していました。今回は、利島よりもさらに南にある小笠原諸島の「母島」にいる3年生の児童がお相手です。
一人ずつ自分が住んでいる島についてテーマにそった発表をしたあと、画面越しの児童が元気よく手をあげて質問し、それに対して発表した児童が、はきはきと答えていきます。「海が好き」という発表に対しては、「海にはどんな魚がいるのか」「海でどんな遊びができるか」といった質問が飛び交い、お互いに興味深く話を聞いていたことが印象的でした。
授業が終わった後に児童へ感想を聞いてみると、
「同じ島だけど雰囲気が違う様子がわかった」
「相手の島に行ってみたくなった!」
という声があがり、児童たちが理解を深め、相手の島に対しても興味を持っていることが伺えました。
今後は、お楽しみ会や夏休みの報告会などを企画されているとのことで、島の児童たちがさらに友好な関係になっていくことが期待できます。
授業を見学して、オンライン授業をはじめた経緯や離島教育についてもっとお話を聞いてみたいと思い、後日、前期課程副校長の亀井久士先生、3年児童を担任する池田莉都先生のおふたりにお話を伺いました。

(左)亀井副校長(右)3年担任池田先生
ー今回オンライン授業を行ってみて、児童の反応はいかがでしたか?
池田先生「最初はかなり緊張している様子でした。授業を行う前に、顔合わせの機会を設けて自己紹介などを行ったのですが、初回から2回目くらいは恥ずかしい気持ちがあったのか、発言も控えめなところがありました。ですが、回数を重ねていくうちにどんどん積極的になっていって…。感想を述べるタイミングで『どうかな?』と思って表情をうかがうと、二人とも『いけます!』という前向きな表情をしているのがすぐにわかって、その成長ぶりには本当に感動しました。」
ーとても頼もしい姿ですね!対面でないからこそ教員の立場ではどのような工夫をされていますか?
池田先生「普通なら職員室の中ですぐに終わるような内容でも、距離が離れている分、オンラインでの打合せとなると少し手間がかかってしまいます。ですが、それも児童のために必要な準備だと考えています。また画面の配置や時間構成なども、段取りを細かく設定して授業に取り組んでいますね。島特有なのかもしれませんが、電波が弱く接続が悪くなったときは正直かなり焦りましたが…。(笑)」
オンラインでの取り組みだからこそ、念入りな事前準備は欠かせません。池田先生の言葉からも「児童たちにいい時間を届けたい」という思いが強く伝わってきました。

教室の外ではツバメが巣作りしている様子
オンライン授業をはじめ、島の教育ではその地域の特性を生かした手段が多く求められます。島で取り組む教育に関して、内地の学校との違いや、今後の課題について伺いました。
ーおふたりとも島以外の学校にいた経験があると聞いたのですが、島と都心部の学校では、どのような違いがあるのでしょうか。
亀井先生「利島では、少人数だからこそ一人ひとりの表情がよく見えます。それによって児童にあわせた個別のサポートができたり、様子をみて声をかけたりということができる。それはやろうと思っても内地ではなかなか難しいんですよね。少人数だからこそ生きてくる教育があって、人数に見合った関わり方が重要だと考えています。」
池田先生「島では児童と先生の距離感が近いという特徴があります。平日は『児童と先生』の関係ですが、休日や島のイベント、放課後一緒にサッカーしているときには『村民同士』という関係に変わります。児童や保護者との関わる時間が長く、距離が近いです。
それから、内地にいた時は『3年生学級の担任』という感覚でしたが、今は『〇〇さんと〇〇さんの担任』という意識が強くなっています。その児童一人に対して考える時間が圧倒的に違いますね。」
おふたりとも島での赴任を希望し、利島で教員をされているそうです。そのためか、島の教育や人との関わりに親しみと理解を持ち、その環境を生かした教育に意欲的に向き合っている姿勢が印象的でした。

亀井先生「今後も積極的にオンライン授業などDX教育には力を入れていきたいと思っています。今回の3年生で良いタイミングで授業内容と絡めてできたのと同じように、他学年でも意味のある授業を気軽にできる環境にしていきたいですね。」
池田先生「そうですね。かまえてやる授業よりも、『休み時間にサッカーしようよ!』と友だちを誘うような感覚で“つながる”ことができたら理想的なゴールかなと思います。」

小さな島の制約を越え、オンライン授業を通して、交流の場が増えることで「つながる学び」が児童たちにも根付き始めています。
画面の向こうにいる友だちとの対話を通して、多様な意見や考え方に触れるきっかけは、島の子どもたちにとって大変重要なことだと感じます。
小さな島、利島から始まる大きな学びの広がりに、今後もご注目ください!