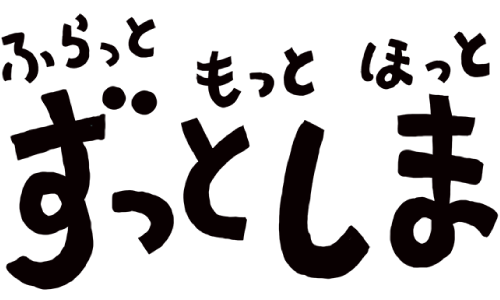


利島小中学校では、給食を校内の調理室で作っています。そこで活躍するのが栄養士の山辺さん。
利島への熱い想いと、はじけるような笑顔がとても印象的でした。
利島では、給食の時間になると山辺さんが各教室(食事場所)を毎日巡回します。
通常規模の学校では全教室を一度に回るのは難しいですが、利島なら毎日全員に会えるのが特色です。
子どもたちにとって山辺さんは、“給食の時間に毎日来る人”です。
「子どもたちの率直な声を直接聞けるのが、私のやりがいです。
『ラーメンが食べたい』『ハヤシライスがいいな』といったリクエストは、できる限り献立に反映しています。
自分の意見が採用される喜びや、“声を出せば届く”という実感を持ってもらえたらうれしいですね。」
顔を合わせる機会が多い分、自然と子どもたちとも打ち解けます。トウモロコシの皮むき体験やパンづくり教室といった給食行事も盛り上がり、楽しい学びの場となっています。
インタビューの中でも、彼女が子どもたちとのやりとりを心から楽しんでいる様子が伝わってきました。

保護者向けの給食試食会に特別参加させていただきました。
子どもたちの食事中の様子を見るために教室を巡回するのも大切な仕事の一つですが、学校給食における栄養士の役割はそれだけではありません。給食全体の統括から子ども一人ひとりのケアまで、多岐にわたります。
文部科学省の基準に沿った栄養管理、学校給食法に基づいた調理工程・衛生管理、食材の発注、温かい料理を温かく提供するための工程設計、調理員さんとのチーム連携など、給食が子どもたちのもとへ届くまでの準備全般を担います。
食物アレルギーや特別食についても、保護者や養護教員、担当教諭と連携し安全を確保します。
また「食材が生産されてから食卓に並ぶまで」を学ぶ機会づくりや、正しい食習慣・食文化の理解を育む役割も担っています。

大人になってから見ると、とても懐かしい給食の風景
利島には飲食店がいくつかありますが、チェーン店はありません。島外に出る機会はあるものの、日常的に触れられる料理の種類は都会の子どもたちに比べると少なくなります。
「新しいものに早いうちから出会うことは大事だと思います。様々な味を経験させてあげたいと思っています。」
「最初は色や食感に慣れず、食わず嫌いもありましたが、担当教諭の声掛けやサポートを重ねるうちに、今では子どもたちの方から『次の“世界の料理”はいつ?』『これは何ですか?』と楽しみにしてくれるようになりました。
続けてきた成果かなと思います。初めての料理でもチャレンジしてみようという心構えが芽生えてる気がします。」
山辺さんの思いは先生方にも伝わり、そして確実に子どもたちへ届いています。
9年生(中学校3年生)の最後の給食は、特別メニューの「ふるさと給食」。
「利島の味を忘れないでほしいなという願いを込めて、利島産の伊勢海老、はんば(海藻)、明日葉など島にゆかりの食材を使って、利島の味、給食の味を忘れないでね!という気持ちを込めて、最後の給食を用意します。」
利島には高校がないため、多くの子が15歳で島を離れます。
旅立ちの直前に食べる給食だからこそ、込める想いはひときわ強くなります。

大人気メニュー「キムタクチャーハン」。キムチのうまみと沢庵の食感が、美味しかったです!
「いつか利島産の食材で、安心して食べられる給食をたくさん届けたい。」と想いをお話してくれました。
地場産業を盛り上げる意味でも、食育として地域の食文化を育む意味でも、とても大切な願いです。
いま利島小中学校の給食で使う食材の多くは島外から仕入れています。
島には自家菜園をしている家庭は多いものの、定期的に出荷する農家は少数。高齢化により、撤退するケースも発生しています。
さらに、給食では衛生面から切り身を用いるのが一般的。利島で魚は手に入っても、切り身に加工する施設がなく、給食では利用しづらいのが現状です。
どのような形で実現できるか。
産地・加工・物流のしくみづくりを、地域と一緒に少しずつ——未来へ向けて、可能性を広げていきたいです。