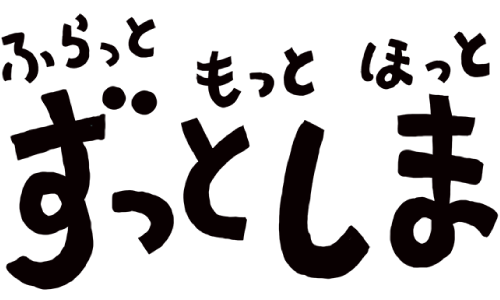


利島では、20〜40代の約84%がIターン(※令和2年1月時点)という、全国でも稀に見る“若い世代の移住者が多い離島”として注目を集めています。
そんな利島で、日々の暮らしを「とても楽しい」と笑顔で話すのが、利島小・中学校の教員・池田莉都さん。彼女自身も、自らの意思で利島を選び、教員として赴任してきた移住者のひとりです。
若い世代が集まる利島の居心地の良さはどこから来るのでしょうか。
池田さんの話から、そのヒントが見えてきました。
ー 池田先生は、自ら利島への赴任を志望されたそうですね。最初に、島で教員をしたいと思ったきっかけを教えてください。
「はい。もともと私は、“特色ある学校”に興味があったんです。具体的には、離島の学校とか、海外の日本人学校、病院内の学級などです。
実は、大学生のときに友人から『一度休学して、シンガポールの学校で働いてみない?』と誘われたことがあって。本気で行こうか悩んでいたんですが、大学の先生に止められました(笑)。でもその経験を通して、“教員にもいろんなキャリアの選択肢があるんだ”ってことを知ったんです。」
ー なるほど。その想いがあって、離島の教員公募に参加されたんですね。
「そうです。内地で教員4年目の時に、東京都の離島教員公募の説明会に参加しました。大島から父島・母島まで、各島の教育委員会等がブースを出していて、直接話が聞けるんですよ。」
ー 数ある島の中で、利島を選ばれた理由は何だったのでしょうか?
「“せっかく行くなら、小規模な離島で働いてみたい”というのが第一にありました。あと、私は理科の研究を続けていたので、赴任後もそれができるかはどうかも大事なポイントでした。
島によっては“船での移動は読めないので、出張はなるべく控えてほしい”と言われるところもあったんです。でも、利島だけは心置きなく“いいよ!どんどんやってください”と言ってくれて。そこで『ここなら、赴任後やりたいことがあっても応援してくれるだろうな』っていう安心感をもてたんです。」
ー 教育に力を入れている利島らしいサポート体制ですね。
ー 実際に利島に来てみて、暮らしにはどんな印象をもたれましたか?
「“利島ってなにもない”って言う人が多いんです。でも、私はそう感じたことがなくて。むしろすごく充実しています。
サークル活動だと、バスケットボールやフットサル、陶芸、太鼓の練習とか…。なんだかんだ、毎日なにかしらの活動があって、楽しい日々を過ごしています(笑)」

ー そんなにたくさん!? すごく充実していますね。
「ほんとそうです。利島って、サークル活動がすごく盛んなんですよ。最近では、ボードゲームのサークルも立ち上がったって聞きました。審査に通れば村から補助金も出るので、申請する人もいるみたいです。」
ー サークル活動って誰でも参加できるんでしょうか?
「はい、すごくオープンです。“これまで何かスポーツやってた?”って初対面の時に聞かれて、『サッカーやってました』って答えたら、フットサルに誘われたり、気づいたらサッカー部の顧問も任されていました(笑)あと、長期出張で来た人が村民の繋がりで活動に参加していることもありますよ。」
ー サークル活動には、皆さんどのくらい参加されているんですか?
「アクティブな人もいれば、家でのんびりすることが好きな人もいるので、本当にその人のスタイルに合わせて選べるって感じですね。必ず参加しなきゃいけない雰囲気でもないし、自分のペースで楽しめます。」
ー サークル活動をしていて、「教員の仕事にもつながっているな」と感じることはありますか?
「ありますね。たとえば、太鼓の練習では子どもと一緒にやることもあって、“今日は先生じゃなくて村民ですよね?”って言われるんです。教員ではなく、“いち村民としての自分”として子どもたちと関われるのは、すごく貴重だと思っています。」
ー いいですね。役職じゃなくて“人としてのつながり”がある感じがします。
「もちろん、子どもとの距離の近さには賛否両論あるとは思います。でも、私は島にいる間はプライベートも含めて島の人と関わっていく方が楽しいかなというスタンスでいます。」

ー 教員だと任期があると思いますが、利島を離れたあとのことも考えていますか?
「はい、できるかは分かりませんが……いつかまた、利島に戻ってきたいなと思っています。
去年4年生の担任をしていたのですが、彼らが“15の春”を迎える前に私は異動予定なんです。子どもたちが15の春で島を離れる時には、彼らが小学2年生のときに担任だった先生と一緒に、竹芝で子どもたちを迎える約束をしています。」
(「15の春」:利島には高校がないため、中学卒業と同時に子どもたちが島を離れることを指す。)
ー 素敵ですね…。子どもたちにとっても、内地に頼れる大人がいるのは大きな安心につながりそうです。
「もうひとつ、今、すごくお世話になっている民宿の方がいて。“いつでもふらっと帰ってきなよ”って言ってくれるんです。娘のように接してくれていて、そういう関係性を築くことができた人がいるので“またこの島に帰ってきたい。これからも利島に関わり続けたい。”と思っています。」
インタビューが終わりに差し掛かったとき、池田先生から教員の間で代々受け継がれてきた一冊の冊子を見せていただきました。
そこには、利島での暮らしの注意点、島ならではの楽しみ方、ちょっとした知恵や心構えまでが丁寧に綴られています。ページをめくるたびに、利島に関わった先生たちの経験と想いが、そっと語りかけてくるようでした。
移住者を温かく迎え入れる利島の文化は、自然に育まれたものではなく、多くの人の手で丁寧に繋がれてきた証なのだと、心から感じました。