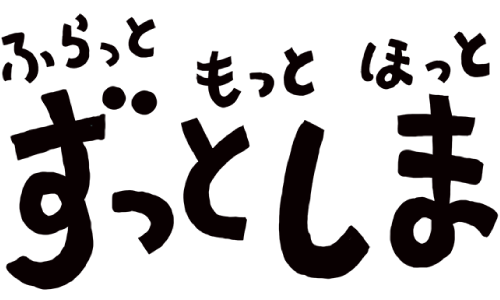


3月末、春の訪れとともに、利島では毎年特別な季節がやってきます。
高校がない利島では、中学校を卒業した子どもたちは15歳の春に島を離れ、本土での新たな生活が始まります。この旅立ちを「15の春」と呼び、子どもを持つ親だけでなく、島全体で子どもたちの門出を見守り、支える風土が根付いています。
今回は、そんな島の子どもたちと日々向き合っている利島小中学校の教員・岩崎正太郎さんにお話を伺いました。
ーはじめに、岩崎先生が教員を目指したきっかけを教えてください。
「そうですね。実は、私はもともと学校があまり得意ではなかったんです。でも、高校時代に出会った社会科の先生を見て、初めて『この大人、かっこいいな』と思いました。その先生は、同じ東京の離島である三宅島の出身だったんですよね。
その先生に『お前は教員に向いているから、目指してみれば?』と言われたんです。本当は大学にも行く気がなかったのですが、その先生が親身になって進路を考えてくれたおかげで、進学を決心しました。
大学ではアメリカンフットボールに打ち込み、卒業後は私立高校で教員をしながら、アメフト選手としても活動していました。」
ーアメフトと教員の両立もすごいですね! しかも、高校時代から島と縁があったんですね。
「そうなんです。さらに面白いことに、教員になって新任の頃にお世話になった先生も八丈島出身だったんですよ。おじいちゃん先生でしたが、とにかく懐が深くて、人としての器が大きい方でした。
これまで出会ってきた尊敬する先生たちが、なぜかみんな島出身だったんです。島に行けば、先生たちの懐が深い理由がわかるのではないかと思い、いつか島に行きたいという気持ちが強くなりました。」
ー岩崎先生が利島に来ることになったきっかけを教えてください。
「島に行きたいという気持ちが強くなった頃、小笠原諸島で働く先輩から声をかけられました。ちょうど島の教員公募があり、応募して合格したんです。ただ、配属先は希望していた小笠原ではなく、まったく情報のなかった利島でした。
正直、最初は戸惑いました。でも、以前勤めていた学校の同期が、利島で数学を教えていたんです。これも何かの縁だなと思って、この島に来ることを決めました。」
ー実際に利島での教員生活はいかがですか?
「最初の担当は、中学1年生の担任でした。子どもたちは素直で、とてもかわいくて、毎日が楽しかったですね。
利島は東京都の中でも珍しく、小学校と中学校が同じ校舎にある環境なんです。もちろん、小学校と中学校ではそれぞれのやり方があり、意見がぶつかることもありました。でも、『15の春』という大きな節目を迎える子どもたちのために、小中が連携して子どもたちを育てることがずっと大切だと感じていました。
そんな中、前教育長や村長が、小学校と中学校を統合し、義務教育学校にすることを進めてくれました。
今は『利島小中学校』として、利島らしい教育の形を模索しています。この島だからこそできる教育にすごく魅力を感じていますし、島の教育は、日本の教育の原点とも言われているので、とてもやりがいがありますね。」

ー利島では島全体で「15の春」を支えていると伺いました。学校ではどのようなサポートをしているのでしょうか?
「後期課程(中学)に上がるころから、『自立とは何か』を意識的に子どもたちに伝えるようにしています。島を離れれば、すべて自分でやらなければならないので、毎月1回、生活・安全・食など、自立に必要なことを朝の会で伝えています。」
ー食についても指導するんですね。
「そうですね。自分の体をつくる食べ物を知ることはとても大切だと考えています。また、進路指導は7年生(中学1年生)から始めています。利島の子どもたちの進路は、親御さんが一緒に本土に移住するかどうかで大きく変わってくるんです。子どもだけでは通学が難しい学校もあるため、全寮制の私立学校を選ぶのか、学生寮に入るのかなど、様々な選択肢について早い段階から家族で話し合ってもらうようにしています。」
ーなるほど、親子で「15の春」を考えることが大事なのですね。
「本当に大切なことです。9年生(中学3年生)になると思春期の真っ只中で、親子の会話が自然と減ってしまうこともあるじゃないですか。だからこそ、早めに情報を集めて、進路を一緒に考える機会を作るようにしています。」

ー島での生活について伺いたいのですが、岩崎先生は休日をどのように過ごされていますか?
「アメフトをずっとやっていたので、ガレージに筋トレグッズを置いてパーソナルジムを作ったりしています。あとは、都心で暮らしていた時に比べて、自分だけの時間が増えたので、プロジェクターを購入して、家で映画を楽しんだりもしています。」
ー島の方々は自宅を工夫して楽しまれているのですね。道を歩いているだけでは気づかないです。
「アミューズメントパークがなくても全然問題ないですよね。今夜も、ダーツバーに改装しているお家にお邪魔するんですよ。子育て世代の家庭では、お互いに集まって食事会をしたり、子どもを預け合ってお酒を楽しんだりと、交流もしやすいんじゃないかなと思います。」

ー島の暮らしは工夫次第でとても楽しめそうですね。
「そうですね。夕日が綺麗な日は山頂にもつ鍋を担いで行って、みんなで鍋を囲んだこともあります。島ならではの遊び方ができるのが魅力ですね。」
ーみなさん遊び方が上手ですね!自然をうまく活かして楽しんでいるのがとても魅力的です。今日はお話を聞かせていただき、ありがとうございました!
「15の春」は、単なる別れではなく、利島という島の文化そのものなのかもしれません。
15歳で島を離れることは、決して寂しい旅立ちではなく、島の人々が支え、見守る中で踏み出す新たな挑戦です。
送り出す側も、送り出される側も、この風土を受け継ぎながら、強く生きていく。
そうして築かれる「つながり」こそが、この島の本当の強さなのだろうと感じました。